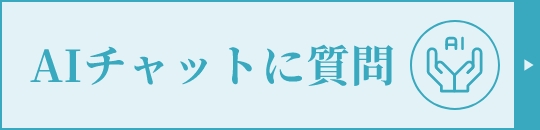インプラント治療におけるボーンレベル製品と流れの違いについて
- 2025年5月6日
- コラム

「インプラントの構造って、実は全部同じじゃないんですか」
そんなふうに思っていませんか?治療を検討する多くの人が、ティッシュタイプとボーンレベルの違いに迷い、どちらが自分に合うのか判断できずに時間だけが過ぎていきます。歯科医院では診療のたびに説明を受けるものの、レベルやアバットメントの構造、サーフェイスの加工など、専門用語が並ぶだけで納得できる判断材料に欠けてしまうのも現実です。
そもそもボーンレベルのインプラントは、歯肉より深い位置に固定される設計が特徴で、歯周組織との接合や周囲の治癒力に優れています。ストローマンなどに代表される製品には、BLタイプと呼ばれる仕様が採用されており、安定性や治療後のメンテナンス性にも差が出ます。しかし、この違いがどんなふうに自分の口内環境に影響するのかを事前に理解できる機会は、意外と限られています。
「違いを知っておけば、こんなに悩まずに済んだのに」
そんな声が多いからこそ、インプラントのレベルに注目した情報は重要です。製品や診療方針だけでなく、治療にかかる時間や患者への負担、周囲の組織への影響に至るまでを知ることが、後悔のない選択につながります。
治療を始める前に必要なのは、専門的でありながら生活者目線に立った知識。続く内容では、代表的な製品の特徴や設備、診療の流れまでを具体的にひも解いていきます。自分の選択に自信を持ちたい方は、ぜひ読み進めてください。
海岸歯科室は、患者様一人ひとりに寄り添い、安心して治療を受けていただける環境をご提供しています。最新の設備と技術を駆使し、虫歯治療からインプラント、予防歯科まで幅広い診療を行っています。お口の健康を守るために、丁寧なカウンセリングと治療計画を立てています。皆様のご来院を心よりお待ちしております。歯に関するお悩みは、ぜひ海岸歯科室へご相談ください。

| 海岸歯科室 | |
|---|---|
| 住所 | 〒261-0014千葉県千葉市美浜区高洲3-23-1 ペリエメディカルビル美浜 3F |
| 電話 | 043-278-7318 |
インプラントにおけるボーンレベルの基本構造を知るために
骨の高さに合わせて設置される仕組みについて
ボーンレベルインプラントとは、インプラント体が歯槽骨と同じ高さに埋入される設計のことを指します。一般的なインプラントでは、インプラント体が歯肉の上部に露出するタイプもありますが、ボーンレベルタイプは骨の高さに合わせて埋め込まれるため、治療後に見た目が自然に仕上がるという特徴があります。
この構造は、歯肉との調和や審美性を求める方にとっては非常に重要です。インプラント体とアバットメントを接続する位置が骨内にあることで、インプラント周囲の軟組織や骨との接触面が長くなるため、長期的な安定にもつながると考えられています。
ボーンレベルインプラントには、プラットフォームスイッチングと呼ばれる仕組みが取り入れられている場合が多く、これによってインプラント周囲の骨吸収を軽減する役割が期待されています。これは、インプラント体とアバットメントの接合部を意図的に狭くすることで、接合部から発生する微小な動きや細菌の影響を骨から遠ざける働きを持ちます。
ボーンレベルとティッシュレベルの構造上の違いを理解することも大切です。ティッシュレベルはインプラント体が歯肉の上まで露出しており、手術回数が少なく済むことが多いですが、ボーンレベルは埋入後に歯肉を切開してアバットメントを取り付ける手順が必要になります。このため、手術工程や期間について事前に把握しておくことが望まれます。
インプラント治療を行うにあたっては、患者の骨の量や質、噛み合わせ、部位の審美性などを総合的に判断して最適なタイプが選ばれます。ボーンレベルインプラントが適用されるのは、特に骨がしっかりしていて、歯肉との調和を重視したい部位、たとえば前歯などです。
このような構造の特性を理解することは、インプラント治療に関して納得感を持って臨む上で重要なステップです。骨との接合位置や手術工程、周囲組織への影響など、多くの要素が関係するため、歯科医師との丁寧な相談が不可欠です。
| 項目 | ボーンレベルインプラント |
| 埋入位置 | 歯槽骨と同じ高さ |
| 接合部の特徴 | 骨内での接合 |
| プラットフォームスイッチング | あり(骨吸収軽減が期待) |
| 手術回数 | 通常2回法(2回の手術が必要) |
| 適用症例 | 骨がしっかりしている部位、審美性が重視される部位 |
| 審美性 | 高い(歯肉との調和に優れる) |
このように、構造面での理解が深まることで、自分に合った治療選択の判断がしやすくなります。骨の高さに合わせて設置されることで、見た目だけでなく長期的な安定性にも関与する点は、信頼性という面でも注目されています。
口の中で見た目や機能にどう影響するか
ボーンレベルインプラントが口の中でどのような影響を与えるかについては、審美性と機能性の両面から捉えることが大切です。見た目に関しては、インプラント体が骨内に埋め込まれていることで歯肉の立ち上がりが自然になり、天然歯のような見た目に仕上げやすくなります。特に笑ったときに歯ぐきが見える方にとっては、この点が大きな安心材料となるでしょう。
歯ぐきの形や厚みに合わせてアバットメントが調整できるため、歯肉との境界が滑らかに仕上がりやすく、自然な歯列を再現しやすい構造です。骨としっかり結合する性質を持つため、装着後の動揺やズレの不安も軽減されます。
機能性の面では、噛む力がスムーズに骨へ伝わりやすいため、日常的な咀嚼動作にも影響が出にくいとされています。ボーンレベルインプラントは、上部構造を支える基盤がしっかりしていることから、固い食べ物を噛んだときの負荷にも耐えやすく、長期的な快適さが得られる点でも支持されています。
前歯部や奥歯では、見た目だけでなく、機能面でのバランスも重要になります。奥歯においては強い力がかかるため、インプラント体と骨の接触面積がしっかり確保できるボーンレベルが適しています。一方で前歯では、審美的な仕上がりと歯肉のラインの維持が求められ、これにもボーンレベルが有効です。
| 部位 | ボーンレベルによる影響 |
| 前歯部 | 歯肉の自然な立ち上がりが得やすく、見た目がきれいに整う |
| 奥歯部 | 咬合圧に耐えやすく、長期間の安定性が期待できる |
| 歯肉ライン | 調和がとれやすく、違和感の少ない仕上がり |
| 咀嚼機能 | 骨との接合が強固で、噛む力の分散性に優れている |
| 装着感 | 天然歯に近い感覚が得られやすい |
ティッシュレベルと比べたときの特長の違い
歯ぐきの形を保ちやすい理由とは
ボーンレベルインプラントは、インプラント体を骨の高さとほぼ同じ位置に埋め込む構造を持ちます。これにより、インプラントと歯肉の接触点が骨内に収まるため、歯ぐきの自然な立ち上がりを再現しやすくなります。ティッシュレベルタイプでは、インプラント体の一部が歯ぐきの上に露出する設計であるため、骨と歯肉の境界を人工的に設定することになります。これに比べてボーンレベルは、軟組織との連続性が高く、結果として審美的に優れた仕上がりが実現しやすいと言えます。
とくに前歯など見た目を重視するエリアにおいて、歯ぐきの形が不自然であると治療後の満足度は大きく下がります。その点、ボーンレベルタイプは、審美ゾーンにおいて歯肉の立ち上がりを滑らかにコントロールしやすいため、美しく自然な見た目を再現する上で高く評価されています。
歯ぐきの厚みや形状が患者ごとに異なることを考慮すると、ボーンレベルはより柔軟に対応できるという利点があります。アバットメントの高さや角度を調整することで、個別の歯肉条件に合わせた設計が可能となり、外科的な処置の自由度も広がります。歯肉のバイオタイプが薄い方や、歯ぐきが退縮しやすい傾向がある方にとっても、構造上有利に働きます。
歯肉に直接接する部分の素材や接合形状も、歯肉の形態保持に影響します。インプラントとアバットメントの接合部が滑らかでマイクロギャップが少ない構造であるほど、細菌の侵入を防ぎやすく、炎症や歯肉退縮のリスクを抑える効果が期待できます。
手術後の経過においても、歯ぐきの厚みや形が維持されているかどうかは、患者が見た目に満足できるかどうかを左右する重要な要素です。ティッシュレベルの場合、歯肉の境目がやや人工的になりやすく、特に歯ぐきの薄い患者では歯肉退縮によって金属部分が露出する懸念もあります。
このような違いは、治療結果に対する患者の満足度に直結するため、治療前の段階で歯科医とじっくり相談し、目的や期待値に応じたインプラント方式を選択することが大切です。
表にまとめると、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | ボーンレベル | ティッシュレベル |
| インプラントの位置 | 骨内(骨の高さと同じ) | 歯ぐきの上に一部露出 |
| 歯ぐきの自然な立ち上がり | 再現しやすい | やや人工的になることがある |
| 審美性 | 高い(特に前歯部) | 比較的低め(部位による) |
| 歯肉の形態保持 | 柔軟に対応しやすい | 歯肉退縮の影響を受けやすい |
| 患者個別対応性 | 高い(アバットメントで調整可能) | 限定的(標準形状に近い) |
このように、歯ぐきの見た目や形を自然に仕上げたい方にとって、ボーンレベルインプラントは構造的にも非常に有利です。審美性と清掃性の両立を求める方には、選択肢の一つとして検討の価値があります。
清掃のしやすさやお手入れの違いについて
インプラント治療を受けたあと、長く健康的な状態を保つためには、日々の清掃やメンテナンスが欠かせません。ボーンレベルとティッシュレベルのインプラントには、お手入れのしやすさという点でもいくつか違いがあります。ボーンレベルタイプは接合部が歯ぐきの下に位置しているため、外部からのアクセスが難しい部分もあります。そのため、歯間ブラシやフロスなどの補助用具を適切に使わなければ、プラークや細菌の蓄積を招くことがあります。
ティッシュレベルタイプはインプラント体が歯ぐきの上に一部露出している設計となっており、接合部の清掃が比較的しやすいという利点があります。しかし、この部分は口腔内に直接接するため、表面が粗いとプラークが付きやすく、炎症を引き起こすリスクも高まります。清掃がしやすいという特徴がある一方で、定期的なクリーニングや専門的なメンテナンスは欠かせません。
ボーンレベルインプラントの構造は、インプラントとアバットメントの接合部が歯肉の下に隠れることで細菌の侵入を抑えやすい設計になっています。特にプラットフォームスイッチングが取り入れられている製品では、接合部の位置を骨より内側にすることで、炎症が骨に波及しにくくなり、インプラント周囲炎のリスクが抑えられるという研究報告もあります。
患者によっては、歯ぐきの厚みや骨の高さ、清掃器具の使い方に違いがあるため、どちらが向いているかは一概に決めることができません。歯科医院では、治療前にCTや口腔内スキャンなどの診断をもとに、それぞれの構造がもたらす清掃のしやすさを総合的に判断します。
ボーンレベルとティッシュレベルでは、使用されるアバットメントや上部構造の形状にも違いがあり、それによってブラシが届きやすいかどうかも変わります。歯科医院によっては、インプラント装着後に患者ごとに最適な清掃器具を提案しているところもあり、清掃指導の質が治療の持続性に大きく影響します。
以下は清掃性における比較です。
| 清掃項目 | ボーンレベル | ティッシュレベル |
| 接合部の位置 | 歯ぐきの下 | 歯ぐきの上に露出 |
| ブラシの届きやすさ | やや難しい(技術が必要) | 比較的容易 |
| 細菌の侵入リスク | 少ない(設計上の工夫あり) | 多め(露出部が広い) |
| プラークの付着しやすさ | 少なめ(表面加工次第) | 多め(露出面が広い場合) |
| メンテナンス頻度の必要性 | 高い(専門的サポートが重要) | 高い(露出部の管理が不可欠) |
サイズや種類による適した使い方
ナロータイプやレギュラータイプの違いを理解する
インプラント治療において、ナロータイプとレギュラータイプという2つの主要な選択肢は、患者の骨の状態や治療目的によって使い分けられます。この選択は単なるサイズの違いに留まらず、治療の成功率やメンテナンス性、さらには審美性にも深く関係します。まずナロータイプとは、主に狭い骨幅に対応するために設計されたインプラントであり、細い構造が特徴です。これに対してレギュラータイプは、標準的な骨幅を持つケースで広く使われており、耐久性や支持力が高いことから、機能面でも信頼性があります。
ナロータイプが活躍する場面は、前歯部や骨量が不足している箇所です。長期間の欠損により骨吸収が進んでいる場合や、骨造成手術を避けたい患者には有力な選択肢となります。逆に、奥歯など咀嚼圧が強くかかる箇所では、より頑丈なレギュラータイプが適しています。
インプラントの直径だけでなく、長さの選定も重要です。ナロータイプには、短いモデルも多く、垂直方向の骨量が限られているケースにおいても対応できます。ただし、細く短いインプラントは応力が集中しやすく、過度な負荷がかかると周囲骨への影響が大きくなるため、補綴設計や咬合バランスを含めた総合的な判断が必要です。
こうした選択には、術前の精密な診査が不可欠です。歯科用CTによる骨幅や骨高さの三次元的評価、歯肉の厚みや周囲組織の安定性も考慮されます。上部構造のタイプや患者の口腔衛生状態、生活習慣(喫煙、歯ぎしりの有無)も、適切なタイプの決定に大きく影響します。
治療計画を立てる段階で、患者と歯科医師の間でこれらの違いとメリット・注意点をしっかり共有することが重要です。特にナロータイプのような特殊な仕様のインプラントを用いる場合は、定期的な経過観察とメンテナンスの重要性を事前に伝えることで、長期的な安定性が高まります。
以下の表では、ナロータイプとレギュラータイプの違いを骨量条件や使用部位、対応可能な症例別に整理しました。
| 比較項目 | ナロータイプ | レギュラータイプ |
| 直径の目安 | 約3.0mm〜3.5mm | 約3.75mm〜4.5mm |
| 使用される主な部位 | 前歯部、骨幅の狭い部位 | 臼歯部、骨量が十分な部位 |
| 骨造成の必要性 | 少ないケースが多い | 場合によっては必要 |
| 対応できる症例 | 骨幅が不足する、インプラント1本症例など | 多歯欠損、フルマウスなど広範囲に対応 |
| メリット | 骨造成の回避、低侵襲 | 高い耐久性、広い適応範囲 |
| 注意点 | 応力集中による破損リスクがある | 骨幅により使用不可のことがある |
歯科医院でよく使われる代表的なタイプ
歯科医院でのインプラント治療において、多く採用されているのはストローマン、ノーベルバイオケア、アストラテックなどの信頼性の高いメーカー製品です。これらには、それぞれレギュラータイプとナロータイプのラインナップがあり、症例に応じて柔軟に対応可能です。
日本国内においては、骨幅や高さの傾向が欧米人と異なるため、比較的細めのタイプが選ばれることが少なくありません。とくにストローマン社のBLT(Bone Level Tapered)シリーズは、ボーンレベルでの埋入に適し、狭い骨幅や前歯部の審美性を重視した症例にも対応できます。ティッシュレベルとの違いが明確であるため、清掃性と審美性の両立を図りやすいという点で評価されています。
国内で使用されるインプラントのサイズ傾向としては、以下のような傾向が見られます。
| メーカー名 | 主な製品名 | 直径の選択肢 | 特長 |
| ストローマン | Bone Level, BLT | 3.3mm, 4.1mm, 4.8mm | ボーンレベル埋入、表面性状が周囲骨と高い親和性 |
| ノーベルバイオケア | Active, Replace Select | 3.5mm, 4.3mm, 5.0mm | 初期固定力が高く、骨質が悪いケースに強い |
| アストラテック | EVシステム | 3.6mm, 4.2mm, 4.8mm | 長期安定性に優れ、歯肉への親和性が高い |
| 京セラ | POI EX | 3.3mm, 4.1mm, 5.0mm | 日本人の骨格に適したサイズ展開 |
これらのインプラントは、患者の骨量や治療目的に応じて選定されますが、選択の際には直径だけでなく長さやネックデザイン、接合方式なども検討対象となります。ネック部がマイクロスレッド構造になっているものは、骨とインプラントの接触面積を増やし、初期固定を強化する狙いがあります。プラットフォームシフティング設計により、歯肉のボリュームを維持しやすくなることも評価されています。
日常的に使用されている代表的なサイズについて、歯科医院ではカウンセリング時に患者へ丁寧に説明されることが多く、その理解の深さが治療に対する安心感にもつながります。特に初めてインプラントを受ける方にとっては、サイズ選定の理由が明確に示されることが、納得して治療を進める第一歩となります。
治療に関わる手順の流れを知っておく
型取りの方法と準備の流れについて
インプラント治療の成功には、正確な印象採得が欠かせません。その中心となるのが、口腔内の型取り作業です。インプラントの型取りには大きく分けて「オープントレー法」と「クローズドトレー法」の2種類があり、それぞれ特徴と適応状況が異なります。どちらの方法も歯科医師の判断により選ばれますが、患者にとってもこの工程の意味や違いを理解しておくことは、安心して治療に臨むために大切です。
オープントレー法は、トレーに穴が開いており、インプラント体にスクリューで直接アクセスしながら位置を固定する方式です。この方法は特に正確性が重視されるケース、例えば複数本のインプラントが埋入されている場面や、アーチ形態に沿った位置関係を再現する必要があるときに選ばれる傾向があります。患者が感じる圧迫感は多少ありますが、精密な再現性が確保できる点で高く評価されています。
クローズドトレー法は、トレーに穴がなく、型取り時にピックアップがトレー内に残らない形式で、主に単独のインプラントに対して用いられることが多いです。簡便な手順で済むため、診療時間が短縮できるという利点があります。特に高齢者や体力に不安のある方、短時間での処置を希望される方にはこちらの方法が適しています。ただし位置の精度ではやや差が出るため、臨床判断が重要になります。
型取りの工程には、患者ごとの口腔内の状態に応じて使用される材料の選定も重要です。現在では精度の高いシリコーン系の印象材が多く採用され、歯肉や粘膜の形状を立体的に再現することが可能です。印象材は流動性や硬化時間の調整が可能で、唾液量が多い方や口の開閉が困難な方にも柔軟に対応できます。
準備段階としては、インプラントのアバットメントを装着した状態で行われるため、事前にアバットメントの形状確認と清掃が徹底されます。こうした準備を怠ると、最終的な上部構造との適合性に影響を及ぼしかねないため、歯科医院側の連携体制が非常に重要です。
以下に代表的な型取り方法とその特徴を整理しました。
| 型取り法 | 特徴 | 主な使用状況 | 所要時間 | 精度 |
| オープントレー法 | トレーに穴を開けてピックアップ | 複数歯や精密さ重視の症例 | やや長め | 高い |
| クローズドトレー法 | トレーに穴を開けずに採得 | 単独歯・短時間対応向け | 比較的短い | 中程度 |
治療が進んでいく一般的な進行の仕方
インプラント治療には複数の工程があり、すべてのステップを理解することで、治療中の不安や戸惑いを大きく減らすことができます。ここでは、カウンセリングから最終的な上部構造の装着までの一般的な流れを順を追ってご紹介します。
治療の始まりは、まずカウンセリングです。ここでは患者の希望や治療に関する質問への回答、治療内容の説明が行われます。口腔内の状況を把握するため、CT撮影やレントゲン、模型の作成が行われ、骨の量や質、周囲組織の状態が詳細に確認されます。この診査結果をもとに、治療計画が立てられます。
次に行われるのがインプラント体の埋入手術です。局所麻酔のもと、顎骨にドリルで孔を開け、そこにインプラントを固定します。この手術は1本あたり30〜60分程度かかるのが一般的で、術後は骨との結合を待つ期間が必要です。これをオッセオインテグレーションと呼び、通常2〜4カ月かけて進行します。
結合が確認された後、アバットメントと呼ばれる接合部の取り付けが行われます。このアバットメントは歯肉の上に出る部分で、最終的な人工歯を支える役割を持ちます。アバットメントの装着時には歯肉の整形が行われ、自然な歯肉ラインを形成することも重視されます。
次の段階は仮歯の装着です。仮歯は審美性の確保だけでなく、咬み合わせや発音の確認を行う重要なパーツです。この段階で不具合があれば、上部構造の形状を微調整する機会として活用されます。
最後に本歯(上部構造)を装着して治療は完了となります。この本歯にはセラミックやジルコニアといった審美性に優れた素材が使われることが多く、見た目も自然で耐久性にも配慮されています。完成後は定期的なメンテナンスが欠かせません。インプラントの周囲炎や清掃不良によるトラブルを防ぐため、プロフェッショナルケアを継続することが求められます。
以下に一般的な治療の流れをまとめます。
| 治療工程 | 内容 | 所要期間の目安 |
| 初診・診査 | カウンセリング、CT撮影 | 1日 |
| 診断と計画 | 骨量評価と治療計画策定 | 数日〜1週間 |
| インプラント埋入 | 顎骨へ埋入手術 | 約1時間(1本) |
| 治癒期間 | オッセオインテグレーション | 約2〜4カ月 |
| アバットメント装着 | 土台の取り付け・歯肉整形 | 1〜2週間 |
| 仮歯装着 | 咬合確認や調整 | 2〜4週間 |
| 上部構造装着 | セラミックなどの本歯を装着 | 1日 |
| メンテナンス | 定期検診と清掃 | 継続的 |
使われている製品や導入されている技術について
よく取り扱われているインプラントメーカーについて
インプラント治療を検討するうえで、使われている製品の種類や特性を知ることは安心感につながります。中でも「ストローマン」は世界的に高い信頼を得ているインプラントメーカーの一つです。このメーカーが評価されている背景には、素材の品質や表面処理技術の高さ、そして豊富な治療実績があります。
ストローマンの製品はチタン素材をベースに、ナノレベルでの表面処理が施されており、骨との結合を早める特徴があります。歯肉の形状に合わせてアバットメントを選択できるため、審美性と機能性の両立がしやすいとされています。特に前歯など目立つ部分の治療には、この点が大きな利点です。
「ノーベルバイオケア」や「京セラ」といったメーカーも日本国内で多く採用されており、それぞれに異なるアプローチや特徴を持っています。ノーベルバイオケアは独自のコネクション方式を採用し、咬合力に対して安定性がある設計が特徴です。京セラは日本人の骨質に合ったインプラント開発を進めており、国内症例に即した安心感が支持されています。
以下の表に、主なインプラントメーカーの特徴を整理しました。
| メーカー名 | 特徴 | 主な採用エリア |
| ストローマン | 表面処理が高精度で骨結合が早い | 世界各国・日本全国 |
| ノーベルバイオケア | 独自のコネクション構造で耐久性に優れる | 欧米・日本の大規模歯科医院 |
| 京セラ | 日本人の骨質に適した製品が多い | 国内全域 |
これらのインプラントはそれぞれに適したケースがあり、骨の状態や治療方針、患者の希望に応じて使い分けがされています。製品選定は歯科医師の診断と方針に基づくものであるため、患者側から無理にメーカーを指定する必要はありません。ただし、自分が受けるインプラント治療でどの製品が使われるかを把握しておくことは、術後のケアやトラブル時の対応をスムーズにするうえでも役立ちます。
同じストローマン製品でも「ティッシュレベル」と「ボーンレベル」のように細かい仕様が分かれており、骨の厚さや歯肉の高さに合わせた調整が行われます。特に審美性が重要な前歯部では、自然な仕上がりになるようにアバットメントの種類や形状も重要視されます。
日本国内の多くの歯科医院では、これらの有名メーカーを導入し、定期的な研修やアップデートを通じて技術の向上を図っています。信頼できる製品と高い技術の組み合わせが、長期間にわたって安定した口腔環境を維持する鍵となります。
治療に用いられる設備や診断機器の例
インプラント治療は、外科的処置を伴うため、安全性と精度を高めるための設備が不可欠です。歯科医院によって導入機器に差はあるものの、近年ではCTやマイクロスコープといった先進機器を活用することで、より的確な診断と精密な治療が行えるようになっています。
三次元的に骨の状態を確認できるCTは、インプラントの埋入位置を正確に把握するために重要な役割を果たします。従来のレントゲンでは平面的な情報しか得られなかったため、神経や血管の位置を避けるためには術者の経験に頼る部分が多くありました。しかしCTによって立体的な画像が得られることで、手術中のリスクを大幅に軽減できます。
マイクロスコープは拡大視野での施術を可能にする装置で、微細な血管や骨質の変化を見逃さずに処置が行えるという利点があります。インプラント周囲の骨や歯肉の状態を詳細に確認することで、感染のリスクを抑え、治癒を促進するアプローチがとられています。
表に代表的な診断機器とその役割をまとめました。
| 機器名 | 目的・活用方法 |
| CTスキャナー | 骨の厚み・神経の位置を三次元的に把握 |
| マイクロスコープ | 拡大視野での精密処置、感染の早期発見に貢献 |
| デジタル印象装置 | 印象材を使わずに口腔内の立体データを取得 |
| ガイドシステム | CT画像を元に作成したサージカルガイドで精度を高める |
これらの機器は、高度な医療機関だけでなく、一般の開業歯科でも徐々に導入が進んでいます。特に都市部の診療所では、患者の不安を取り除く手段として、設備面での充実を図る傾向があります。
診断機器の導入は初期費用がかかるため、治療費に反映されることがあります。ただし、手術時間の短縮や精度向上、治癒の早期化といったメリットを考慮すれば、結果的に患者にとって大きな価値をもたらす選択と言えるでしょう。
設備の整った歯科医院では、治療前のカウンセリングにおいて、これらの機器を使用する目的や期待される効果について丁寧に説明してもらえることが一般的です。不明点や不安があれば、遠慮せずに相談し、自身の治療に対する理解を深めることが重要です。こうしたやりとりを通じて、インプラント治療はより安心して受けられる医療となります。
まとめ
インプラント治療を検討している方にとって、ボーンレベルという言葉は聞き慣れないかもしれません。しかし、この構造は歯科治療の安全性や美しさを左右する重要な要素の一つです。歯肉の下にインプラントが設置されるボーンレベルの仕様は、周囲の歯肉と自然に調和しやすく、治療後の見た目や衛生面での効果が高く評価されています。
ティッシュレベルとの違いを理解していないまま選んでしまうと、メンテナンスの難しさや長期的な安定性に不安を感じることもあるでしょう。アバットメントの接合部やサーフェイスの設計、そしてインプラント体のタイプによって、使用される製品や治療計画は大きく変わります。これらを事前に知っておくことで、納得感のある選択ができるようになります。
ストローマンに代表されるボーンレベルインプラントは、近年多くの歯科医院で採用されており、設備面でもCTやマイクロスコープといった高精度な診断機器が導入されていることで、患者ごとの診療の質が向上しています。診療の初期段階での型取り方法や、治療ステップごとの時間配分に至るまで、患者への負担を軽減する工夫が数多く施されています。
安心して治療を受けるためには、自分の口内環境や希望に合ったインプラント構造を選ぶことが欠かせません。構造の違いや製品の特徴、治療設備の内容を正しく理解することで、無駄な不安を減らし、損失を防ぐ判断ができるようになります。歯科医との相談をスムーズに進めるためにも、今回触れた知識は、これから治療を考える方にとって確かな助けとなるでしょう。
海岸歯科室は、患者様一人ひとりに寄り添い、安心して治療を受けていただける環境をご提供しています。最新の設備と技術を駆使し、虫歯治療からインプラント、予防歯科まで幅広い診療を行っています。お口の健康を守るために、丁寧なカウンセリングと治療計画を立てています。皆様のご来院を心よりお待ちしております。歯に関するお悩みは、ぜひ海岸歯科室へご相談ください。

| 海岸歯科室 | |
|---|---|
| 住所 | 〒261-0014千葉県千葉市美浜区高洲3-23-1 ペリエメディカルビル美浜 3F |
| 電話 | 043-278-7318 |
よくある質問
Q. インプラントのボーンレベルとティッシュレベルでは、通院回数や治療にかかる期間はどれくらい変わりますか?
A. ボーンレベルは歯肉より深くインプラント体を埋め込む構造のため、術後の治癒時間や安定期間が若干長くなる傾向があります。診療の進行ではアバットメントの装着や印象採得などのプロセスが丁寧に行われるため、ティッシュレベルに比べて通院回数が一度増えるケースもあります。ただし、治療の進行は患者の骨の状態や周囲の歯肉の厚みによって異なるため、個別診断が必要です。治療期間に余裕を持ってスケジュールを立てると安心です。
Q. インプラント治療で選ばれるストローマン製品のボーンレベルは、他の製品と比べて何が優れているのでしょうか?
A. ストローマンのボーンレベルインプラントは、BL表面処理技術や接合部の気密性が高く評価されています。周囲の歯肉や骨に与える影響が少なく、長期的な安定性を重視した設計です。特に歯科医療現場で導入されているサーフェイス技術は、治療後の骨との結合力を高めることができるため、患者の満足度が高い傾向があります。ストローマンは世界中の臨床データと研究結果に裏打ちされた製品であることから、信頼性を重視する方に広く選ばれています。
Q. 骨が薄い場所でもナロータイプのボーンレベルインプラントは使用できますか?
A. ナロータイプのボーンレベルは、幅が限られている部位や前歯部などの骨の幅が狭い箇所で特に効果を発揮します。レギュラータイプよりも細く設計されているため、歯肉の厚みや骨量が少ない症例にも対応できます。もちろん、事前にCTなどの診断機器で正確な骨の厚みや高さを確認し、治療計画を立てることが前提となります。タイプの選択は見た目や機能性にも直結するため、医師との十分な相談が不可欠です。
Q. ボーンレベルのインプラントは見た目にどんなメリットがありますか?
A. ボーンレベルはインプラント体を歯肉の内部に完全に設置するため、天然歯に近い見た目を再現しやすいという利点があります。歯肉のラインが自然に仕上がることで、笑ったときに金属部分が露出しにくく、美観に優れた治療結果が得られます。特に前歯など審美性が求められる部位では、ティッシュレベルよりもボーンレベルのほうが選ばれるケースが多くあります。審美と機能性のバランスを重視する方にとって大きなメリットです。
医院概要
医院名・・・海岸歯科室
所在地・・・〒261-0014 千葉県千葉市美浜区高洲3-23-1 ペリエメディカルビル美浜3F
電話番号・・・043-278-7318