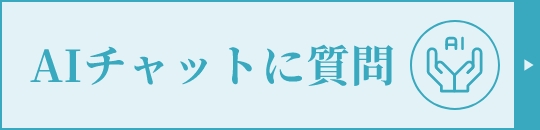-
- 2024.11.28
- お知らせ
ホワイトニングサロンオープンのご案内
-
- 2024.08.16
- お知らせ
休診のお知らせ
【重要】8月16日(金)は、大型台風接近に伴い休診とさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
-
- 2023.11.02
- お知らせ
移転のお知らせ
2023年11月2日(木)より稲毛海岸駅南口のペリエメディカルビル美浜に移転致します。
南口を出て左側にある交番前の道を渡った新規ビルの3階です。移転先住所:
千葉県千葉市美浜区高洲3-23-1 ペリエメディカルビル美浜 3F

お知らせ