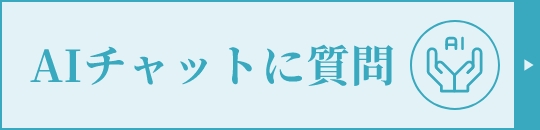お茶を飲むとなぜ歯が黄ばむのか?黄ばみの原因と対策を徹底解説!
- 2025年3月14日
- コラム
お茶を飲み続けていると、歯がだんだんと黄ばんでくる。そんな経験はありませんか?
なぜ、お茶やコーヒーを飲むと歯の色が変わってくるのでしょうか?今回はそんな疑問を解説していきます。
なぜお茶を飲むと歯が黄ばむのか

なぜ、お茶を飲むと歯が黄ばむのでしょうか?その原因はお茶に含まれているポリフェノールにあります。
原因はポリフェノール
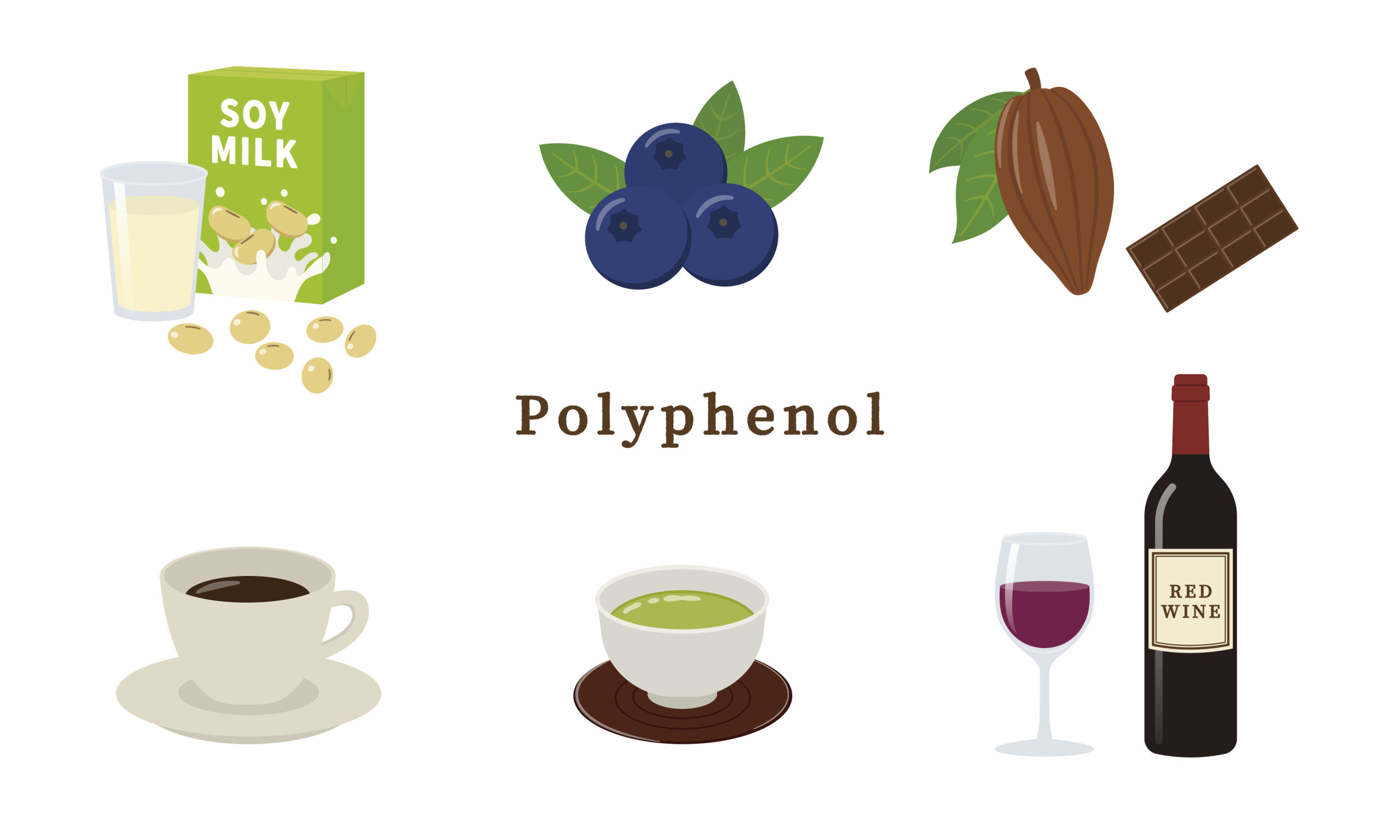
お茶にはタンニンと呼ばれるポリフェノールの一種である色素が含まれています。その色素が歯に付着し蓄積していくことでステインに変化。歯がそのステインにより変色してしまうのです。
ペニクリと着色汚れ
では、なぜポリフェノールは歯に付着してしまうのでしょうか。これには歯の表面を覆っているペリクリという唾液の成分で構成された膜が関係してきます。このペリクリがポリフェノールを引き付け、歯に付着させてしまうのです。付着したポリフェノールが蓄積していきステインが徐々に形成されていくのです。
着色しやすい歯の特徴
お茶で変色しやすい歯には特徴があります。どのような特徴を持つ歯が、お茶で変色しやすい歯なのでしょうか?その特徴について解説していきます。
エナメル質が薄い
欧米と比べて日本人の歯はエナメル質が薄く中の黄色い象牙質が透けて見えるようになっています。そのため、日本人の歯は黄色く見えてしまうのです。
さらに加齢によってエナメル質はすり減り、中の象牙質が透けて見えるので変色しやすくなります。エナメル質に細かい傷がついても、そこに着色汚れが付着し歯が変色してしまう原因になってしまいます。
歯磨きが不十分
歯をきちんと磨かない人はそうでない人に比べて、歯に色素が着色しやすい状態にあります。特に歯と歯茎の間の汚れは、きちんと磨かないと取れにくい場所ですよね。
そこに茶渋が溜まり着色の原因となります。
歯は時間をかけて隅々まで掃除するようにしましょう。あまり力を入れず歯ブラシを軽く充てるぐらいの感覚が適切です。歯を強く擦りすぎてしまうと表面に細かい傷が出来てそこに汚れが溜まりやすくなってしまうからです。
着色しやすい飲食物をよく摂取する
着色しやすい飲食物をよく摂取するのも、歯が変色しやすい原因の1つとなっています。具体的にどのような飲食物を摂取すると歯に色素が着色しやすくなるのでしょうか。
代表的な食べ物を詳しく見ていきます。
お茶
お茶にはポリフェノールの一種であるタンニンが多く含まれています。
タンニンは渋み成分で、歯に付着すると歯磨きでは落ちにくい頑固な汚れです。タンニンは緑茶やウーロン茶、紅茶に多く含まれています。
コーヒー
コーヒーには独特の香りや苦みの元となるクロルゲン酸というポリフェノールが含まれています。このクロルゲン酸には動脈硬化や糖尿病の予防を促すメリットがある一方、色素沈着しやすいというデメリットも併せ持っています。そのため、コーヒーをよく飲む人は歯の色が変色しやすいのです。
赤ワイン
赤ワインにもポリフェノールの一種であるタンニンが含まれています。赤ワインはエイジングケアや健康にいいといわれている飲み物ですが、着色しやすい飲み物でもあります。
また含まれるアルコールにより、表面のエナメル質が溶けやすくなってエナメル質の下の黄ばんだ象牙質が見えやすくもなります。
チョコ
チョコレートに含まれているカカオポリフェノールも汚れを付着させてしまいます。
ポリフェノールには抗酸化作用もあり、エイジングケアも期待できますが食べ過ぎ歯の変色を助長してしまいます。
カレー
カレーに含まれウコン(カーメリック)は天然の着色料として知られています。そのため、カレーは黄色い色をしているのです。食後すぐに歯磨きなどをすれば色素は沈着しません。ですが放っておくと歯が茶色や黄色に変色してしまいます。
また、着色料を使っているお菓子やジュース。色素の濃い調味料である醤油やケチャップ、ソースも歯の着色の原因になりやすいです。
歯の茶渋を取る方法
歯についてしまった茶渋はなかなか取れません。どうすれば、これらの茶渋を取ることができるのでしょうか。今回は自宅でおこなうケアと、歯科医がおこなうケアに分けてこれらを解説していきます。
自宅でおこなうケア

自宅でおこなうケアの中心は歯ブラシや市販のホワイトニング用品になります。それらのケアの仕方について解説していきます。
ホワイトニング成分配合の歯磨き粉を使う
普通の歯磨き粉では茶渋はなかなか落ちません。ですが、ホワイトニング成分配合の歯磨き粉であれば茶渋を落とすことも可能です。茶渋で悩んでいる方は是非ともご利用ください。
歯専用の消しゴムやホワイニングトペンなどを使う
歯の消しゴムは文字通り、歯の汚れを消すためのホワイトニング用アイテムです。歯磨きで落ちなかった茶渋もこれであれば落ちるかもしれません。
ホワイトニングペンも同様に歯をキレイにするアイテムです。こちらは歯のマニュキュアのように、歯を塗装して歯を白く見せるものになります。
電動歯ブラシを使う
ステイン除去などの機能がついた電動歯ブラシを使うと、茶渋などをキレイに落とすことができます。ただし振動が強いため研磨剤などが入った歯磨き粉を使用することはおすすめできません。歯の表面が傷ついてしまう可能性があるからです。
歯磨きに電動歯ブラシを使用するなら、研磨剤の入っていない歯磨き粉を使用しましょう。
歯間ブラシ・デンタルフロスを活用
歯間ブラシやデンタルフロスを使用して、歯と歯の間に詰まった汚れを除去することができます。特に歯間ブラシやデンタルフロスは歯磨きでは届かない部分もキレイにしてくれるため、茶渋による着色防止に役立つでしょう。
特に歯間の汚れは長い時間放置すると着色の原因となるため注意が必要です。
最近では、ホワイトニングケアを目的としたデンタルフロスも登場しています。軽い歯間の着色汚れであれば落ちる効果が期待できますので、日ごろ使用するようにしてみましょう。
歯科医師がおこなうケア

自宅でおこなうケアの歯のケアの他に歯科医でおこなうケアもあります。専門医による着色汚れのケアにはどのようなものがあるのでしょうか?
歯のクリーニング
着色した茶渋はなかなか落ちてくれません。そんなときに役に立ってくれるのが歯科医院のクリーニングです。クリーニングによって、歯と歯のすきまや歯茎の間の汚れもキレイに落としてくれます。白さを維持したい場合は1ヵ月に1度は行きましょう。
PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)
PMTCとはProfessional Mechanical Tooth Cleaningの略称です。これは、自由診療のクリーニングとして扱われているものです。歯科医院やクリニックで、フッ素が配合された研磨ジェルや専用の機材を使用し歯を磨くことを指します。歯の表面だけでなく歯と歯根の間や歯間のプラークを取ることも可能です。
施術後はプラークだけでなく、茶渋やヤニなどの着色もキレイに取れます。
ホワイトニング
ホワイトニングは特殊な薬液を使って歯の色素を白くする方法です。ここではオフィスホワイトニングとホームホワイトニングについて解説します。
オフィスホワイトニング
オフィスホワイトニングとは歯科医院やクリニックでおこなわれるホワイトニングのことです。特殊な溶液を歯に塗布しLEDの光を照射することで、歯の色素を変化させます。即効性があり、すぐに歯の白さを実感できるのが特徴です。
ホームホワイトニング
ホームホワイトニングはマウスピースに薬剤を塗布し、それをつけることで歯に薬剤を浸透させ歯を白くする方法です。時間はかかりますが歯のすみずみまで白くなりますし、なにより色戻りが少ないのが魅力的です。
やってはいけない着色汚れの落とし方
これまで自宅でできるケアの仕方や歯科医院のケアの仕方を解説してきました。ここでは、逆にやってはいけないケアの仕方を解説していきます。
重曹を使う
重曹を使う歯のクリーニング方法は他の記事だと推奨されていたりもします。ですが、重曹で歯を磨くと顆粒の影響で歯に傷がつく場合があります。歯の1番外側にあるエナメル質が傷ついて摩耗してしまうと、虫歯などのリスクも高くなってしまいます。
一方で重曹を使ったうがいは口内を中和し、虫歯に効果があるとされています。ただし、うがい後に歯磨きをしないことに注意しましょう。
クエン酸を使う
クエン酸は柑橘類系の果実や梅干しなどに含まれる酸味成分です。掃除にも使われる成分であるためか、歯の茶渋除去に効果があると紹介されることもあります。
たしかにクエン酸には、アルカリ性の汚れを分解する働きがあります。
ですが、クエン酸自体が強い酸性なので歯のエナメル質を溶かしてしまう恐れがあるのです。クエン酸で歯を磨くと一時的にははは白くなりますが、長期的には歯の健康を害し虫歯のリスクを高めてしまいます。
茶渋を予防する方法
歯をキレイにしても、またお茶を飲んで茶渋が歯についてしまったら意味がないですよね。そうならないためにするにはどうしたらいいのでしょうか?
茶渋を予防する方法を解説していきます。
口をゆすぐ
お茶を飲んだ後の口内にはポリフェノールが大量に残っています。
茶渋などによる歯の着色を防ぐためにも、お茶などポリフェノールが大量に入った飲み物を飲んだ後は、水で口をゆすぎましょう。摂取後にすぐにゆすげば、色素沈着も抑えられます。
ホワイトニング剤の入った歯磨き粉を使う
ホワイトニング剤の入った歯磨き粉を普段から使ってみましょう。
普段からシリカやポリリン酸といった着色汚れを落とす成分が配合された歯磨き粉を使っていれば、茶渋による歯の着色も抑えてくれるでしょう。
ガムを噛んで唾液を出す
唾液は歯の細菌や汚れを洗い流してくれる役割があります。
そのため、ガムなどを噛んで唾液の分泌を促すことで着色汚れの予防をすることができます。虫歯の発生が気になる方はキシリトールガムを選びましょう。
定期的なクリーニングを歯科医院で受ける
定期的なクリーニングを歯科医医院で受けることで、茶渋の沈着やプラークの蓄積を防ぐことができます。茶渋の予防だけでなく、歯周病や虫歯の予防にもつながるのです。3ヶ月に1度を目安に受診するといいでしょう。
まとめ
今回はお茶を飲むとなぜ歯が黄ばむのかについて解説いたしました。
記事の前半では、お茶に含まれるポリフェノールの一種であるタンニンが茶渋の原因になること。記事の後半では茶渋などの汚れを取るにはどうしたらいいのか。ケアの仕方や予防方法をお話いたしました。
海岸歯科室では定期的な歯のクリーニングなども承っております。歯の茶渋を予防したい方は、是非とも当院のクリーニングをご利用ください。
監修:理事長 森本 哲郎